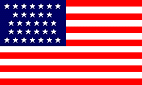

新選組! 雑文コーナー
その六
DVD 『新選組! 完全版』 によるレビュー
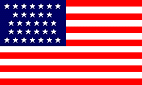

| 2005年9月9日 ☆新選組! 第二回 多摩の誇りとは さて舞台は安政四年(1857年)、調布の宮川家。近藤は多摩への出稽古の徒次、里帰りしているという設定。宮川勇五郎が登場して、勇とその兄宮川音五郎に、拳骨を口に入れる芸をねだり、史実の近藤勇の特技を、ここで香取慎吾にサービスさせる。これあるがゆえに近藤役を香取慎吾に当てたという、まことしやかな話もあるほどだ。他方、音五郎役の阿南健治もまた、「竜馬におまかせ!」で近藤勇に扮したこともあり、やはり口に拳固が入って適役だ。宮川勇五郎は音五郎の子であり、長じて板橋における近藤の処刑の目撃者となる。後に近藤の娘たまと結婚し、子母澤寛に対する語り部となる人物だから、そのあたりを知っていると、この場面はにやりとする。また近藤に従って出稽古について来た沖田みつが姿を見せる。どこにでも現われるみつだが、ここで子供と遊ぶ姿は、総集編たる「新選組!スペシャル」のナレーター役として、導入部で子供たちの遊ぶ姿を眺めるシーンの原型となるのだろう。 |
三大キャラクター登場す
| 2005年11月2日 ☆新選組! 第五回 婚礼の日に |
| 2005年11月4日 ☆新選組! 第六回 ヒュースケン逃げろ 新選組! というこのドラマを深読みする面白さにはたと気付き、初めて長々と感想を書いたのが、この第六回だった。異人ヒュースケンの登場という華やかな要素も、それに与っておそらく力があったろうとも思われる。ともかく、私にとっては記念すべき回なので、そのときどういうことを記したか、あらためて部分的に引用しておきたい。 “ ヒュースケンが、自分のマントを羽織った土方歳三に「よくお似合いです」と言う場面。 あれはつまり、土方の運命を暗示しているわけだ。土方は函館で戦死する直前、洋装で写真を撮っている。これが土方のイメージを決定づけていることは周知の通りで、五稜郭のミスター土方祭りは、必ずあの格好で登場する。また、マントはつねに「死」のメタファーでもある。 つまりヒュースケンは、死人が狂言回しとして登場したようなもので(わざわざ「今は助かったが、私はいずれ斬られる」と予言めいたセリフを言う)、いわば土方の死に様を予告する役回りとして、三谷幸喜が出したというわけだ。” (2004年2月15日 雑文その一 ☆新選組! 第六回より) それでは、一年と九箇月になんなんとする時間を閲して、ここにあらためてレビューをしてみよう。 ドラマの日付は一八六〇年(萬延元年)九月三十日となっている。ヒュースケン暗殺は十二月五日のことなので、かれに残された時間は、あと二箇月という時点での話となる。 序幕は、勇と歳三と周助が、府中六所宮における天然理心流扁額奉納記念興行に出発する場面から始まる。姑ふでに叱られながらも自分のペースと位置を確立していくつねに、小姑的存在のみつが太鼓判を押す(「あんたなら大丈夫だわ」)。勇の世話役を奪われて、いささか残念な面持ち。府中では興行も成功し、首尾よく手にした収入を分配しながら、小島鹿之助が公武合体などの時流を説明する。一方、市ヶ谷試衛館では、留守の沖田に対してインテリ山南が時勢を解説しようとするが、ともに行動できる大人として勇に認めてもらいたく、それゆえ剣の道ひとすじの沖田には、難しい時代の動きなど、所詮理解の範疇の外だ(「よくわかりませんよ」)。 だがここでの山南の役割は、解説役というよりもむしろ板付として、尊皇攘夷の風潮がはびこる中で「異国人も斬られる……」と、視聴者に本編の始終を予告することにあるのである。 じつは舞台の本筋は、この扁額奉納興行という大イベントの後、勇と歳三の遭遇する、ある事件に置かれる。 府中からの帰り道、たまたま休んだ茶店で卵が買い占められているところから、異人ヒュースケンとその妾お富の噂を聞き込む、勇と歳三。女と来ればたちまち興味津々の土方は、渋る近藤を引っ張ってその家を覗きに行くが、いきなり怪しげな浪人たちに捕われてしまう。あわや危機一髪の瞬間、二人の前に現われたのは、旧知の永倉。浪人たちは清河八郎の配下の薩摩人で、永倉とその友人市川宇八郎は食い詰めた揚句、異人成敗の助っ人として雇われていたのだった。 事情を聞いた近藤は、たちまちいつもの無鉄砲な義侠心を発揮する。「稼がねば生きていけない」と言う永倉に、「あなたの剣が泣く、闇討ちは卑怯、残念です」と食い下がり、なおも喧嘩別れの帰り道、諦めきれずに「武士は卑怯な真似をしてはイカンのだ、とくに永倉さんはイカンのだ」と言い出して、襲撃に先んじて警告を発すべく、妾宅へと来たるヒュースケンを待ち受ける。 ちなみにこの「とくに永倉さんは」という科白は、まるで季布の一諾とでも云うべき、互いの気性を分かり合った同士としてのもので、それは最終回の永倉の「(近藤さんを悪く言えるのは)俺だけだ」という科白と、遠く離れて照応する。またこの二つの場面において共に傍らにいるのが、まったくそうした機微を理解しない浅薄な市川宇八郎=芳賀宜道であるというのも、出来過ぎといえば出来過ぎな設定だ。 馬に乗ってやってくるヒュースケンを近藤は止めて、事情を説明する。「なぜ(嫌いな異国人である)私を助ける」と尋ねるヒュースケンに、近藤は「卑怯なことは嫌いだ」と応える。「あなたは誠の士(さむらい)だ」と賞賛するヒュースケン。じつは「新選組!」を通して、「誠」ということばが出るのはここが初めてで、そしてこのことばが他ならぬ米国通訳ヒュースケンから発せられているということこそが、このドラマの鍵なのだということに、くれぐれも留意しておかなくてはならない。 とはいえヒュースケンは近藤に「私が助かったとして、残った女性はどうなる」、見殺しにするのは卑怯ではないかと切返して、近藤はぐっと詰まる。「武士よりも武士らしい」心、「己の幸せのみを考えて生きられない」心の持ち主は、異国人の中にもいるのだ。いやそんな心性を持っているところからすると、定めて「お前日本人だろ」と突っ込む土方の科白は、川平慈英ヒュースケンに対する傑作楽屋落ち。 しかしそうは言っても、黒船来航までは平穏だった日本をこんなに引っかき回したのは、やはりお前たちにっくき異人だ。だが武力ではとうていかなわない。それで近藤は土下座して、「早く日本から立ち去ってください」と頼む。「トシ、お前も早く!」と急かされて「お願いしマース」と気のないお辞儀をする土方。 ヒュースケンは嘆息し、「この国はなぜ殻に閉じこもるのか」「井の中の蛙大海を知らず」ではいけない、この美しい国を世界に知らしめたい、「もっと自信を持ちなさい!」と長広舌を振るう。そしてピストルに弾は込めていない、刀を銃で撃てるか、私の国にも武士道はあると誇りを示す。 駆け戻った近藤は、永倉一味の説得にかかる。「(ヒュースケンは)ワリとイイ奴」「あれは誠の士(さむらい)だ」「血の通った人間、心から日本を愛している、われわれ以上に」と。そして「日本の女を手込めにして居るのだぞ」という難詰に対しては「ある国への愛を表現するのに最適の方法は、そこの女を好きになることではないですか」と抗弁する。ところでこの科白、なにか典拠がありそうな気もする。 「私はあなた(永倉)を救いたい、大勢で金目当て、そんなことをして欲しくない」必死の近藤に、世間のあらを食って生きてきた永倉も、さすがに辟易しほだされる。「近藤さん、あなたはあまりにまっすぐ、あまりに幼い。だから心に突き刺さる」この人の天真爛漫な愚直さを見守り、十全に輝かせてやらねば。後に近藤勇の使徒となる永倉の、回心の瞬間だ。 舞台はクライマックスを迎える。ヒュースケンに襲いかかろうとする薩摩侍、「私の問題だ」とサーベルを抜くヒュースケンを制して示現流と切り結ぶ天然理心流の土方、「気が変わってこちらにつく」とのっそり進み出る永倉。勝負はついたが、市川宇八郎だけはなおも「俺は十両欲しい!」と打ちかかり、てもなく近藤に撥ね飛ばされて、こうして永倉を除く三人は、ほうほうの体で逃げて行く。 「素晴らしいものを見せてもらった、日本の武士は世界一強い」と感激するヒュースケンに、近藤は自信を取り戻した笑顔で、「井の中の蛙大海を知らず」には後がある、それは「されど空の高さを知る」だと教えるのだ。 どこまでも高い空、羽織と同じ青い色の空に、これから近藤と新選組は飛翔していくのだ。 舞台は終局。買い占めた卵を使って、習い覚えた洋食を焼くお富の背後から、マント姿のヒュースケンがそっと抱きしめる……と思えば、マントを羽織っていたのは土方で、この悪戯は「異人の抱いた女」に対する好奇心満々の土方への、ヒュースケンからのちょっとした返礼なのだ。 満足してマントを返す土方に、ヒュースケンが「とてもよくお似合いです」と言う。「どこで買える」「どこでも買えるようになりますよ」日本の、また土方の運命を示す預言的な科白が続き、最初に述べたように、ここで私ははたと観劇の妙味に目覚めるのだ。 そしてヒュースケンの最後の預言が来る。「たぶん私は死ぬ、しかし後悔はしない、この国の土になれることを神に感謝したい」と。 こうして永倉を試衛館の客分に迎え、ドラマの幕は閉じられるのである。 さてこのようにあらためて観なおすと、今回のヒュースケンの役回りは、単に昨年私が見て取ったような土方の先触れどころではない、より深いものを持っていると思われる。 それというのも、ヒュースケンは近藤との会話の中で日本を語るさいに、金魚だの蛙だのとさまざまな例を持ち出すが、ドラマ最終回、土壇場で処刑を待つ近藤が、順繰りに目と心に刻み付けていくものどもは、まさにこれと照応しているのである。しかも近藤が見上げる高い空、それこそはかれ自身がヒュースケンに言った「されど空の高さを知る」の空なのだ(だからその空に永遠に飛躍する蛙として近藤を捉え、(次に何をしようか)という気組みで最後の科白「トシ……」を吐いたと述べる香取慎吾の感覚は、極めて鋭いのだ)。 そこで話をまとめれば、要するに近藤が最後に想起するのはヒュースケンとの邂逅の体験なのであり、そのヒュースケンとは、最初に近藤のことを「誠の武士」と呼び、みずからもまた dicent な gentleman として振舞う人物なのである。人は己を知る者を知る。ヒュースケンは近藤の資質を見出し、近藤もまた、ヒュースケンをおのれの鏡像として認識する。 こうして dicent=誠の心、gentleman=誠の武士という図式が成立し、これはすなわち第一回で考察した星条旗が誠の旗であることと同様になって、このドラマの背後に隠れるモチーフの存在が、この回でもふたたび明らかになったと、私は考えているのである。 蛇足: ●清河役白井さん、ちらっと登場、やはりいい。 |
| 2005年11月7日 ☆新選組! 第七回 祝四代目襲名 主要人物のキャラクターが、ほぼ定まってくる。また、軽佻だが直情で善良な名脇役、望月亀弥太が introduce される。 舞台の幕開けは、土佐勤王党の会合場面から。武市半平太・望月亀弥太登場、武市はあまり熱意のない龍馬に、土佐の同士を募るための血判状を托す。 打って変わってのどかな朝。風来坊の左之助の寝ぼけ顔が、その気分を強調する。一八六一年(文久元年)八月二十七日は、前回からはや一年経っていることを示す。 ここから導入部分。府中六所宮での襲名披露試合が進行していく。平助も現われ加勢。試合の前の打ち合わせで、山南に「守りにつけ」と命ずる土方。兵法にも明るい山南は「攻めるに如かず」とここでは土方を黙らせるが、これからほとんどの場面で常に留守を強いられる山南の姿が、はやくもここにある。勝手に祝い酒を振舞う捨助が邪魔な半端者扱いを受けるのもいつもどおり、左之助もいつのまにか飛び入りし、これ以後左之助と永倉は、つねに二人一組の相互補完的キャラクターとして行動していく。 試合は江戸組が多摩組を圧倒、周助の嘆声「スゲーなあいつら」は後年の浪士組~新選組を暗示するし、また池田屋事件のさいに見物の捨助が発する奇声「スゲー!」にもつながる。 これを見兼ねた総大将近藤は、陣太鼓役の塾頭沖田を投入、沖田は天才振りを発揮して永倉と平助を電光石火に撃破し、そしてとうとう、かつてひねられた相手である山南を打ち負かす。額のかわらけを割られて、よく成長したなと言わんばかりの山南、顔を輝かせる沖田。この場面にはじつは、予告編で紹介されているように、タイミングが合わずに何度もNGを出した後にようやく成功したという、藤原竜也と堺雅人の裏話もあるわけだ。 結局合戦は多摩組の逆転勝利となり、舞台は中盤の展開部分、府中宿へと移る。まずは宴会から締め出されている、沖田と平助の年少コンビの会話。「沖田さんがうらやましい」平助は最後まで変わらずこの思いを抱き続ける。それに答える沖田の科白もつねに同じで、(たとえ総司と改名したって)「悩みはある、子供扱いだ」。 ところで「新選組!」では、沖田は平助が劣等感を抱く対象として、このように間接的に描き出される/浮かび上がらせられる場合も多く、これは第二十七回のエピソード(沖田に化けて茶屋遊びをし、勇に諭され励まされる)や、第三十九回の感動的場面(沖田に痛めつけられる周平を泣きながら庇う)、それに第四十回の両人の別れの場面に至るまで一貫するものであるから見逃せない。 ちなみに、本ドラマにおいては、三谷幸喜は沖田の扱いをどうするか、もっとも苦慮したように思われる。というより有り体に申せば、三谷幸喜の唯一の設定し損ないが、この沖田なのである。 それが証拠に、沖田のキャラクターの特徴的な部分は、みな他のメンバーが分け取りにしてしまう。剣の天才としては斎藤がいる。マスコットとしては平助、後には周平がいる。気楽さならば、原田がいる。単純な正義感の持ち主なら、大石がいる。純真さという面で見れば、平助はもっと純真だ。またたとえ鴨とお梅に翻弄されたからと言って、それ以後かれが人生観を変えたようにも思われず、むしろ変わった部分は勇に取られている。「大人になりたい」がために右往左往してついに倒れるといっても、新選組の隊士のほとんどが、勇も含めて、結局そうした存在ではないか。 とはいえ、その身にまつわってきたフィクションを剥ぎ取っていくと、実在の沖田はまことに没個性な人物になってしまうという不利な点もあることは否めない。三谷幸喜はもちろんそうした先人の貼りつけた虚飾などは使いたくないだろうし、そうかといって一番組組長の沖田を出さないわけにもいかない。ごく最近(2005年11月現在)でも、あるブログでは、「組!」の沖田についてひとしきり話題となっていたというのも、かれの人物設定におけるこうした致命的欠陥、というよりも間接的に描くしかない難しさにあるかもしれない。*雑文 その五 69☆新選組! 第四十九回(最終回)の考察のこの部分をも参照されたい。 結局のところ私が思うに、沖田という人物は、近藤との師弟関係という文脈中に置いてのみ扱うにはいいのだが、このドラマの如き群像劇の登場人物としてはきわめて印象が薄くなるか、あるいは決定的に浮いてしまうのである。 閑話休題。府中宿に話を戻すと、宿場女を揚げて騒ぐ宴席が描写され、いつの間にやら紛れ込んだ左之助がはしゃぎ、朴念仁の山南は振られ、勇は一つ覚えの髑髏を描いている。ここに一瞬市ヶ谷試衛館の情景が挿入され、「どうせ帰りは明日、男なんてみんな同じ」というふでに「あの人はそんなことはありません」と答えつつ、つねは稽古着に髑髏を刺繍している。その背後に縁起の飾り物としてか、鬼瓦の置き物が置かれているのが見え、ともに魔除けである髑髏と鬼瓦とを重ね合わせて、勇を象徴する(鬼瓦が僻邪であることについては、雑文 その三 37☆最後に死ぬのは……?の考察、また雑文 その五 69☆新選組! 第四十九回(最終回)の考察、また雑文 その六 6-01☆新選組! 第一回 黒船が来たの考察を、ともに参照せよ)。 宴席はさらに進み、みつまでが騒ぎに加わっている。そこに周助が、勇に講武所教授の口がかかっていることを披露する。これは桂小五郎(狷介だが人の評価はできるのだ)から松平主税介への紹介で、身分は直参。いくら「武士より武士らしい百姓」とは言っていても、目の前に本式の武士身分がぶら下がって、勇も悪い気がするはずはない。しかし暗い顔になった土方は、そっと席を外す。 ここで土方の描写に行く前に、もうひとつ面白い小起伏が挿入される。すなわち左之助の加入のエピソードだ。祝いの献杯を差し出された周助が「誰だ?」と訝り、永倉が「思い出した!」と叫ぶ。かつての雇われ用心棒対雇われ夜盗の面白さ。そして勇に対しても傍若無人に「あんたのことなんか今すぐにはわかりゃしねえよ、だがここにいる連中見たらわかる」「決めたぜ、客人になってやる」と言い放つ。この場の人々に共有されている、分け隔てない信じ合ったつながりを、不羈奔放な左之助は見て取るのだ。そしてそのつながりはじつは近藤というただ一点に集中しているのだが、しかし新選組が隆盛になった後、その近藤に(そして土方に)権威主義による統率という面が見えたそのとき、すなわち左之助が近藤のことを「わかった」ときから、かれの心はしだいに乖離してゆく。そしてとうとう、甲陽鎮撫隊での脱退訣別(このドラマでは)という悲劇を迎えるのだ。その意味からも、この左之助加入の場面とかれの性格描写は、ドラマ全体の重大な伏線を成しているのである。 さて宿屋の暗い庭先では、土方がひとり物思いに沈んでいる。そこに周助が現われる。飛躍していく勇とおのれとのあまりの対比に打ちのめされ、「カッちゃんに俺はもういらない、剣は沖田、頭は山南がいる」と弱音を吐き訴える土方。それに対して周助は、「山南の知識は書物からのもの、お前には生きた知恵がある。勇は一人で悩みすぎる、倅の力になってやってくれ」と励ますのだ。恐らく生涯初めて人から評価され、頼りにされたであろう、このドラマの土方。かれに新たな自信を与え、未来の姿勢/行き方を決めたのは、じつは近藤周助という、人情に長けた「大きな父」なのだ。 この場面は土方と近藤の会話につながり、「俺はいつまでたっても同じ所にいる」と土方がかこつと、近藤は「俺だって」「時代が動こうとしているのにこのままでいいのか」と答えるが、土方は「俺に言わせりゃゼイタクな悩みだ」と切って捨てる。時代の大きな飛躍に較べれば、古い時代の身分制度に基く小さな出世など、相対的には無いも同然だが、地べたを這いまわっている土方からすれば、そんな見方は到底納得できない。かれはこれから、つねに実際的なアドバイス、ときには苦言を呈する毒舌家としての役割をこなして行くことになるのだ。 いよいよ舞台はクライマックス、変転の場面に移行する。龍馬と亀弥太(「亀と呼んでください」)が宿屋に来訪するのだ(ということは、龍馬は甲州路をとるつもりなのか、それとも小金井から北上して中山道に出るつもりか)。二人は勇と土方に土佐勤王党の血判書を見せながら、攘夷について熱っぽく語る。乗せられた勇「あなたがうらやましい、私も加えてください」龍馬「多摩勤王党でも作ったら」これは後の自由民権運動を視野に入れた楽屋落ちだが、なかなか含蓄のある科白。思えば日本のどの地域でも、豪農、豪商、下士、草莽はみな勤王をスローガンに政治参加を目指し、そうして「夜明け前」に描かれる如く、薩長藩閥政府に使い捨てられていくわけだから。 ところが亀がつい調子に乗って血気に逸り、異国人は皆殺しだと口走ったものだから、すでにヒュースケン(この時点ではすでに死んでいる)を知った近藤としては、持ち前の正義感からしても、黙っていられなくなる。「皆殺しはどうでしょうか」「異人も血の通った人間、追い払えばいい、殺さなくとも」「坂本さんは、こんな奴らの仲間になってもいいのか」この一本気さは、永倉を説得したときとまったく同様だ。鼻白む亀。決まり悪げな龍馬に、すっかり冷静さと自信を取り戻した実際的観察家の土方が追い討ちをかける。「坂本さん、黒船ではしゃいでいたのは誰だ」「アンタは勢いに流されているだけ、図星だろう」何かをやらねばとは思っているが、それが何かはいまだ定まらない、そうした点ではここの龍馬は近藤とさして変わらない。そこを土方は慧眼に突くのだ。黙ってしまった龍馬に「坂本さん、なにヘコンドルです?」と土佐方言でいぶかしむ三宅弘城亀の演技はじつにうまい。 ここに立ち聞きを見つかったみつと捨助が加わり、場面は一挙に破局のドタバタへと駆け上がる。揉み合いの中で血判状を掏り取る捨助、それを奪い返そうとする亀、立ちふさがる勇。龍馬「お前んでは太刀打ちできぬ、ワシが相手じゃ」(亀と近藤は、後に池田屋で再び立ち合うことになるが、そのときも全く相手にならない) 抜刀して撃ち合う龍馬と勇(香取慎吾は江口洋介並みに上背があるようだ)。だが龍馬はすぐに刀を納め(「ヤメじゃヤメじゃ、さすがは天然理心流宗家、こんなところで命は落としたくない」)、血判状を見事に二つに破いてしまう。 去って行く二人を見ながらみつが「血判状などまた書き直せる」と指摘すると、土方が「そんなことは百も承知」「この人(勇のこと)は、坂本が土佐勤王党に加わって何か始めだしたのが嬉しかったから見逃した」と、ふたたび両者を見切るのだ。 「飲みなおそう」と近藤が言って、一場の嵐は過ぎ去る。 終幕は、翌日の市ヶ谷試衛館。ふでは周助の襟の匂いをかぎ、源さんも白粉の匂いに叱り飛ばされる。「男はみんな同じ」「(井戸端で)洗ってきましょうか」決まり悪げな勇。失望と悲しみに目を見張りながらも、つねは「これお使いください」と、夜なべで刺繍した髑髏の稽古着を勇に差し出す。感激した勇は、あらためて妻に対するいとおしみを湧き上がらせつつ、稽古着をつねの肩に着せかける。これからはつねもまた、近藤の魔除けとして、かけがえのない存在となるのである。 |
| 2005年12月22日 ☆新選組! 第八回 どうなる日本 非常に筋の錯綜した一回。大きく見ると前半と後半に分かれていて、前半は後々の回のための伏線張りと人物の性格設定とに費やされ、「どうなる日本」という表題に関わる本筋は、劇のクライマックスに凝縮して置かれる。とはいえ、この表題は近藤の科白として序盤と終局に登場することできちんと平仄がついているし、その近藤の問題意識はそもそも山南に起因するものであるというあたりが、やはり後の回の伏線を成しているのである。 時は文久二年(1862年)5月29日、ところは江戸。土方の見合い話にからみ、多摩の情景も挿入される。さらには伊東大蔵、佐々木只三郎、松平主税之介といった曲者キャラクターたちが紹介される。 舞台は試衛館、食客たちのお国振りを示す納豆談義から賑やかにはじまる。そこに藤堂平助が登場し、近藤は嬉しげに「藤堂さんじゃないですか」と、もう一膳食事を仕度させる。一度婚礼祝いの口上を述べに来ただけの自分を、勇が覚えてくれていたということに感激する平助。これが今回のサブストーリーのひとつの鍵となる。一方、梁山泊化していく道場のありさまに渋い顔をするふでに対して、つねは「食客とはいざとなったら命も投げ打つものです……と何かで読みました」と、それとなく教養を示しながらやりこめる。しだいに刀自の地位が入れ替わりつつあるようだ。 序幕が終わり、劇は前半部に入る。ここにいくつかちりばめられた伏線の中で、最も重要な意味合いを持つのが、すぐに描写される山南の行動だ。 寺田屋事件を引き合いに出しながら騒然たる時勢を解説する山南の話を聞いて、近藤は「いったいこの国はどうなるんだ……」と歎く。ここぞとばかりにその機を捕え、山南は近藤に『日本外史』を贈呈してその気を引き、そろそろと本題に持ち込んでいく。「清河八郎を御存知ですか」北辰一刀流の同門・先輩であり、同時に尊皇攘夷の虎尾の会の指導者でもある清河と一度会ってくれ、と山南は近藤をたきつけ、懸命に自分と同じ理想の道に引き込もうとするのだ。だが近藤は清河がヒュースケン暗殺の黒幕であることを知っており、そうしたやり方には、当然のことながら批判的だ。さらには講武所教授就任の話も目前にあるわけで、いまひとつ気乗りのしない近藤の前に、この山南の試みはひとまず頓挫する。 次に語られるサブストーリーは、平助の移籍問題。もともと沖田と試衛館に憧れている平助は、近藤が名前を覚えてくれていたというだけで、道場を変えることを決断する。それというのも、川向こうの伊東先生は、平助のことを「そこのお前」とか「左から二番目」とかしか呼んでくれないからだ。沖田「近藤先生は近所の犬の名前さえ覚えている」落胆する平助「私は犬以下か……」 近藤は講武所詣でで不在となるため、平助の身柄の受け取りに出向く塾頭沖田は、永倉に近藤のふりをさせて連れて行こうというつもり。しかし世間ずれした永倉は「こういうことはまっすぐにやらねば」と駆け引きに対する自信は満々だ。「オレ行ってやろうか」と枕絵を見ながら言う、なんでもやりたい左之助のことを誰も相手にしない短い一幕は、第四十回における高台寺党分裂のとき「なぜオレを誘わネエかなあ」とぼやく左之助の姿に、遠くその影を落としている。 ここからは、平助問題と講武所問題とが交互に挿入され、しかもそこに多摩の土方見合い問題まで挟まれて、いささか展開が目まぐるしい。 まず講武所に面接を受けに行く勇に、周斎先生がまいないの包みを持たせる場面。勇がはっと気がつくと、掛け軸が消えている。門出を送るつねに、「いくさじゃないんだから」と苦笑し(真の「いくさ」は京都で待っている)、生まれる子供の名前は「多摩に因んで男ならたまお、女ならたま」と言いつつ、勇は出かけて行く。 伊東道場では大蔵先生と加納鷲雄(早くもここで登場していたのか)が、移籍交渉の相手となっている。平助の譲渡を突っぱねる伊東に向かって、ぬけぬけとした顔で「こちらの塾頭とそちらの代表と立ち合って決めましょう」と提案する永倉。コメディアンのグッさんがその片鱗も見せずに真面目に人を食った演技をすれば、コミカルな二枚目半が持ち味の谷原章介もまた、冷酷狷介な美形の役どころを巧みに演じる。 一方、日野の佐藤家では、渋る土方にのぶが見合いの話を押しつける。ちなみにこの場面は千葉県立「房総の村」でのロケで、この民家はかつて下総で実際に使われていた豪農の屋敷を見学用の施設として移築したもので、いまも寝起きとまではいかないものの、限りなくそれに近い形で(農作物の栽培、収穫、保存など)、かつての日常生活文化を生きた姿で復元公開しているものだ。この秋に訪れたばかりなので、あらためて馴染み深い。 次に舞台は、市ヶ谷試衛館でのみつとつねの会話、それに左之助とふでの絡みの場面となるが、ここでふでが捨ててしまえと文句をつけるのが、土方が置き放しにしている石田散薬の薬箪笥で、これが後の本編に重要な役割を果たす小道具となるので見逃せない。 さて芝居は観客に容赦無くずんずん進行し、講武所へと移る。松平主税之介と佐々木只三郎が登場し、ニヒルな佐々木只三郎は、虚飾に寄りかかる松平主税之介や講武所の実態にじつは絶望しきっていて、近藤に「講武所にはあまり多くを期待しない方がいい」とアドバイスする。道場を覗いた近藤が見たものは、若い旗本武士たちのたるみきった姿。意外な思いの近藤の背後から佐々木は「これが実情です」「心を失っている」と吐き捨てる。 このように、このドラマにおける佐々木只三郎(井原剛志ははまり役だ)は、幕府の限界をとうに見切ってはいても忠実な幕臣としてのスタンスを失うことを潔しとはせずに、旧弊な武士身分/生き方にあえて殉じていき、そのことによって近藤勇をさらに引き立たせるという、なかなか渋い役どころを担うのだ。後にかれが江戸で清河八郎を斬る使命を引き受けるのも、清河が幕府を騙してまんまと手玉に取ったのを怒ってだし、またもっと後に京都で坂本龍馬を斬るときは、龍馬が大政奉還を実現させて幕臣の権威と存在意義を雲散霧消させてしまったことに対して怒りを抱いてのことだ。そうした佐々木の性格設定も、すでにここでなされている。* *第三十二回補遺も参照せよ。また第三十六回にも典型的な佐々木像が描写される。 場面はまたもや川向こうの伊東道場に戻り、沖田が加納を打ち負かす。驚いて目を見張る伊東大蔵。とたんに今度は多摩の見合いの場面に転じ、顔を上げたお琴の美貌に土方が目を見張る。 なぜこんなに目まぐるしいのかというと、それは「一目惚れ」ということを対比させんがためだ。というのも、次の瞬間、舞台はふたたび伊東道場となって、伊東大蔵はこう言うのだ。「(平助の)代わりにキミをいただく、いずれは尊皇攘夷のために京へ上る、そういう若者を探していた」と。それに対して沖田がすかさず狙い澄ましたように「私は名前も覚えない人の所へは行きたくありません」と一発皮肉を見舞うと、伊東大蔵は意外なことに「沖田総司」と応える。つまり伊東は、すぐに名前を覚えるほどに沖田の才能に一目惚れしてしまったというわけだ。この「惚れる」というのが、小さいながら本編のサブテーマであり、上にも述べたように、土方はお琴に惚れ、伊東は沖田に惚れる。またこの劇の順序からすれば、そもそも平助が近藤に惚れている。さらに言うならば、じつは山南もまた近藤にとうから惚れているのだが、最初の二者の単刀直入振りに比して、山南はいかにもこうしたことに無様なインテリらしく、本などを渡して相手の気を引こうとするというところがまさにかれのキャラクターを表わしていて、しかもそれはたしかに、京での明里とのやり取りにまで、はるかに響いているようだ。 話を戻して、もちろん沖田がこんな申し出に同意するはずもなく拒否すると、伊東は「この話はここまで!」と席を蹴ろうとするが、そこに割って入るのが加納鷲雄である。「それはいけません先生、いさぎよく約束は守るべき」いさぎよく、卑怯なことを嫌う、誠実な人間としての加納の人物像もまた早くもこの時点で確立され、近藤狙撃のときにも、また流山でのクライマックスのときにも一貫する。 とまれこうして平助は、「身柄貸し出し」という形ながら、首尾よく試衛館への移籍がかなうこととなるのである。 一方、土方は河原でお琴に「オレは嫁を貰うつもりはない」と格好をつけるが、それは妻帯できるほどに将来の展望が開けていないからでもあるし、また同時に妻帯してしまって将来を制約されたくないからでもある。「自信の無さ」と「野心」という、青春期に同居する相矛盾する二つの思いは、男にとっては普遍的な記憶だろう。だが女にそんな気持ちが通じるはずもなく、「私が嫌いならそうおっしゃって下さい」と歎き訴えるお琴の襟足につい目を奪われた土方は、「嫌いだから言っているのではない」「お琴さんはいい匂いがする……」などと言いながら、とうとう自制心を失う。ところで、お琴役の田丸麻紀は、出番こそ少ないが、同じくチョイ役の幾松菊川玲よりははるかにいい。 さてここまでが長い前半部で、ここからドラマは突如後半の本筋に入り、しかも一気に、かつ急速に展開していく。 試衛館に戻った勇の許に、信州松本藩士である伊藤軍兵衛が訪ねてくる。松本藩はエゲレス公使館警備に当たっており、浪士の不穏な動きが伝えられる中、もし戦闘となったさいの特効治療薬として石田散薬を買いたいというのである。どうやら行商時代の土方が、勝手に試衛館を代理店に仕立てていたらしいという設定で、これでドラマ前半の、土方置き土産の薬箪笥という小道具が生きてくる。 薬の運び役は勇と源さん、それに原田。みつはいつも通り、勝手に一行に加わる。ひとり反対のふで(「母上は攘夷派ですか」)は「みんな私を目の仇にして!」と怒るが、そこに意気揚揚と戻ってきた沖田・永倉・平助の姿に、「(食客が)マダ増えるか!」とさらに怒りを募らせる。 公使館への道のり、「(異人どもの傍若無人には攘夷浪士ならずとも往生する、)まだ私がエゲレス人を殺して腹を切った方が……」とひとりごちる伊藤軍兵衛は、すでに狂気を孕んでいる。空を見上げる源さん「一雨きますか」勇「雨の匂いだ」これはもちろん、血の雨が降ることのメタファーだ。 公使館へ着いた四人が聞いたのは、「軍兵衛は責任の重さに神経を病み、任を離れていて、扱いに困っている」という意外な知らせ。要領を得ず帰ろうとするところに、イギリス水兵が二人入ってくる。かれらとたちまち意気投合するみつと左之助、おっかなびっくりの源さん、渋い顔の勇。一方、軍兵衛はノイローゼが嵩じ、ついに耐えられなくなる。 イギリス水兵からシャンペンを振舞われ、例のコルクは酒の蓋だったのかと謎が解けて喜ぶ勇、左之助の故郷伊予の金毘羅様の歌も出るなど、場はしだいに打ち解けていく。「見知らぬ国に来て、苦労も多いだろうな」と源さんに言う勇の述懐は、後の浪士組~新選組の京での労苦を暗示する。 そしてクライマックス、ついに伊藤軍兵衛が乱入し、止めに入る近藤たちの努力も空しく、二人の水兵は軍兵衛の槍の穂先に貫かれる。攘夷ですらない、意味のない犠牲。降りしきる雨の中、石畳に倒れた水兵の体を抱き、勇は絶叫する。「この国はいったい、どうなっていくんだ……!」 |
以下準備中